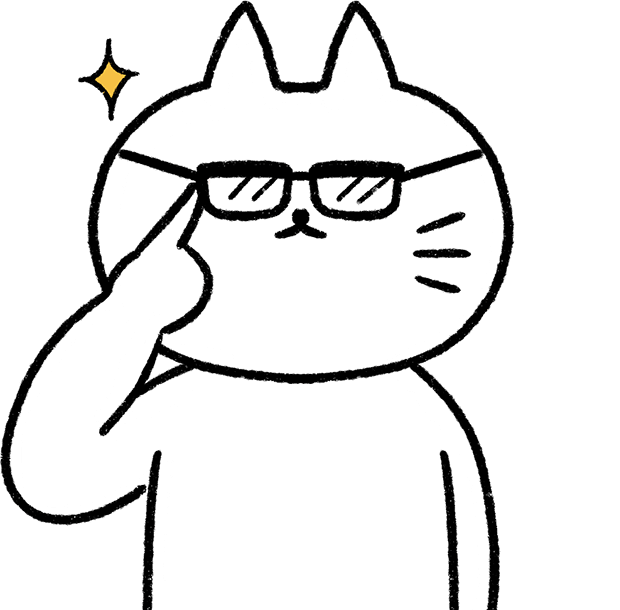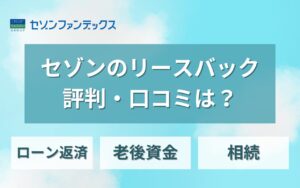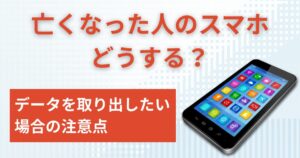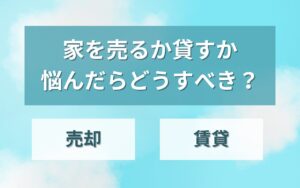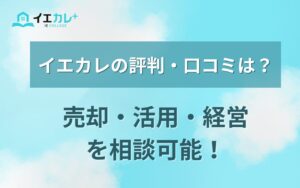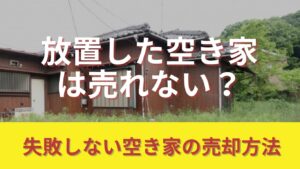最近はスマホやパソコン、SNSやクラウドに大切なデータを残す時代。でも、もし自分や家族が亡くなったあと、そのデータはどうなるか考えたことありますか?
写真や動画、メール、SNSアカウント、ネット銀行…これらは「デジタル遺品」と呼ばれ、放置するとトラブルや情報漏えいのリスクにつながることも。
この記事では、デジタル遺品の基本から、生前にできる準備、死後のトラブル回避方法、専門業者の活用まで、
誰でもわかるように完全ガイド形式で解説します!
家族の負担を減らし、安全にデジタル資産を整理するためのステップを一緒に見ていきましょう。

デジタル遺品整理については、えんがわの生活の知恵担当「こてつ」が解説!大切な人のデータだからこそ、大切に取り扱っていきましょう!
デジタル遺品とは?
デジタル遺品は耳にしたことはあるけど、どういった定義があるのか、スマホやPCはなんとなく想像はつくけど、それ以外にも何か何か相当する物あるのかなど、気になるところを解説!
また、近年デジタル遺品が注目される背景についても、詳しく紹介します。
デジタル遺品の定義
「デジタル遺品」自体に明確な定義はないとされていますが、電子機器とされるパソコン、スマホを始め、カメラやゲーム機、また、インターネットにつなぐためのWi-Fiなども含まれます。主に、オンラインと呼ばれるもので、保存されたデータやSNSなどのアカウントを指します。
これらは、デジタルの「遺品」という取り扱いになるので、スマホやPCなどの有形の遺品は相続の対象にもなり、解約や名義変更などのタイミングも税金が絡むと複雑です。
デジタル遺品の種類
デジタル遺品の種類は、主に2種類に分けられ、以下の有形のデジタル遺品と無形のデジタル遺品に分けられます。
有形のデジタル遺産としては、スマホやPC、タブレットに加え、スマーウォッチやスマート家電、デジタルカメラ、USBやSDなどのメモリーカードなども含まれます。
また、無形のデジタル遺品では、SNSアカウントやメールアドレスを始め、写真や動画、音楽などのデータやサブスク契約、Webサイトのデータなども含まれるようです。また、最近ではネットバンキングや電子マネーも主流なので、それらもデジタル遺品となります。



スマホやPCくらいしか思い浮かばなかったけど、凄く多岐に渡りますね…!サブスク契約や電子マネーもデジタル遺品に入るのは驚きです!
近年注目される背景
近年では、社会のデジタル化の進展が急速に進んでいることから、オンラインの情報や資産が遺品として相続対象になる機会が増加していることが挙げられます。
その中でもよくあるのが、オンラインのサブスクやネットバンキング、仮想通過など、デジタルでの空間に存在する財産たちです。金融資産であれば相続手続きをしないとすぐに凍結されて、相続できなくなってしまう可能性も高いです。
それらのことから、昨今ではデジタル遺品が注目されています。
デジタル遺品に関するよくあるトラブル
ここでは、デジタル遺品に関するよくあるトラブルについて、4つのポイントに分けて詳しく見ていきましょう。
デジタル遺品整理で困っている人は、ぜひ読み進めて見てくださいね!
パスワードがわからずアクセスできない
まず多くの人が感じるのが、パスワードがわからずアクセスができないことです。
スマホから始まり、SNSのアカウントやGoogleやYahooなどのアカウントパスワード、ゲームなどのパスワード、サブスク契約時のパスワード、ネットバンクのパスワードなど、パスワード1つをとってもジャンルは多岐に渡ります。
それらにアクセスできないとなると、デジタル遺品の相続は複雑化します。
昨今では、プライバシー保護や他者からの乗っ取り、不正アクセスの観点から、たとえ親族であっても個人のスマホやアカウントなどのパスワードはほとんどが解除できない仕組みとなっています。
スマホであれば、契約しているスマホのキャリア(docom、au、SoftBank)に相談しても本人以外のパスワードの解除は難しく、デジタル遺品整理業者に相談し、解決するしか方法はありません。
また、スマホ以外にもSNSアカウントやその他メールやネットバンキング、電子マネーのパスワードなどもある場合は、デジタル遺品を専門に取り扱っている業者に依頼し、アカウントの削除や引き継ぎ、銀行などを調べてもらう必要があります。
それに加え、どんなサブスクに契約しているかも全容が不明な場合は、それらを解約してもらう手続きを踏む必要もあるでしょう。



パスワードは重要な個人情報なので生前に共有しない人も多く、9割以上の人が準備をしていないと言われています。勝手に解除されたくないといった意見も多く、難しいところです。
ネット銀行や電子マネー・暗号資産が相続できない
ネット銀行や暗号資産の相続についてもよくあるトラブルです。
銀行、暗号資産ともに、オンラインでの取引となるため、一般的な銀行やゆうちょなどのように実店舗を持っておらず、対面での相談ができないのが基本です。
また、これらのデジタル資産と呼ばれるものは、現実世界では形がないため相続人が存在に気づかないケースも多く、それが大きなトラブルとなることがあります。特に仮想通貨などは、レバレッジをかけて取引をしていた場合、資産がマイナスになている可能性もあり、早めに対処しておく必要があります。
デジタル資産に気づくことができずに放置していると、相続税の追加や損失が発生することも考えられます。それに加え、他者からの不正アクセスによって、資産が奪われる可能性も少なくありません。
故人のネット銀行や暗号資産について把握できていない場合は、専門家に相談し、どのようなデジタル資産があるかをまずは把握することが大切になります。



スマホやPCくらいしか思い浮かばなかったけど、凄く多岐に渡りますね…!サブスク契約や電子マネーもデジタル遺品に入るのは驚きです!
SNSやメールアカウントの放置
亡くなった後のSNSやメールアカウントの放置についても、トラブルとなりがちです。
基本的に、SNSアカウントは本人以外に何かしらのアカウントの管理権限を持っている人が行動を起こさない限りは、ネットワーク上に残り続けることとなります。
また、メールアカウントについても、基本的に本人以外のアクセスは難しいとされており、Gmailなどは必要書類を揃えて、複雑な手続きを終えればアクセスも可能になりますが、必要書類の条件なども複雑なので、簡単ではありません。
Yahoo!メールは、セキュリティーポリシーが非常に厳しく、本人以外は相続人でもアクセスができない仕様となっています。海外では、裁判を起こしてようやくメール内にアクセスできたケースもありますが、ほぼ不可能と思っておいた方が良いでしょう。
各種SNSやメールなどのアカウントなどは、生前整理の際に記録として残しておくのがおすすめです。ID・メールアドレスとパスワードをまとめてメモして、終活ノートに書いておいたり、家族に手紙で伝えておくのも良いでしょう。
遺言書などの公的証書などに記載するのは、複数人が見ることができ、プライバシー保護の観点からもあまりよくないので、信頼できる家族の1人に依頼することをおすすめします。



不正アクセスを防ぐためにも、故人の死後、日にちが経っていないタイミングでSNSアカウントやGoogle・Yahoo!アカウントは削除or自身の管理にしておきましょう。IDやパスワードがわからない場合は、業者に依頼して停止してもらうのがおすすめです。
データ漏えい・不正アクセスの危険性
デジタル遺品のトラブルとしては、データ漏えいや不正アクセスのトラブル事例も少なくありません。
先ほどまでに紹介してきた、ネット銀行や電子マネー・暗号資産、SNSアカウントやメールのアカウントにおいても、そのまま放置し続けると、第三者の不正アクセスのリスクが高まります。
特にSNSなどは、個人情報の流出の危険性もあり、亡くなってからも詐欺やなりすましの被害に遭うこともあるのです。
また、ネット銀行や電子マネー・暗号資産などの場合は、長期間放置していると不正アクセスを狙われやすく、資産を失ってしまうことにもつながりかねません。被害に遭う前にまずは各種デジタル遺品のアカウントを把握し、早めに相続対策を進めておく必要があります。



本当は引き継がれるはずだった資産なども、不正アクセスがあれば一瞬で失ってしまう可能性もあるので、早めに対処をしておきましょう。
生前にできるデジタル遺品対策
デジタル遺品については、残された家族が相続手続きをスムーズに進められるように、しっかりと準備しておく必要があります。
ここでは、相続におけるデジタル遺品の生前対策について詳しく解説します。
パスワード・IDの整理方法
各アカウントのパスワード・IDの整理方法についてです。
現在終活やエンディングノートとしてよく使われている、コクヨやダイソーの自分の情報をまとめておくノートにも、これらを記入する欄があります。
しかし、それらのノートにもIDは書く欄があってもパスワードについての情報を書く欄はない、もしくはプライバシー保護の観点から、最初から塗りつぶされています。各種アカウントでのパスワードの記載方法は、以下がおすすめです。
「アカウントにアクセスする場合はIDを入力し、パスワードは再発行をお願いします」
と別で書いておくと良いでしょう。相続するアカウントによっては、他者からの再発行をNGとしている場合もありますが、パスワードが不正に流出しないためにも、生前対策としては安全に管理する必要があります。
どうしても生前にパスワードを伝えておきたい場合は、封筒などで封をした中の紙にIDとパスワードを記入し、その上から修正テープで一度パスワードを塗りつぶして消しておくと、必要な時に関係者だけが見られるようになります。
修正テープは、乾けば上からスクラッチカードのように擦ることで、また文字が見えるようになるので、おすすめです。



生きているうちに情報漏えいしてしまうと、トラブルになりかねないのでパスワードの管理は慎重に行いましょう!
デジタル遺言書・エンディングノートの活用
現代では、デジタル遺言書やエンディングノートの活用が推奨されており、アプリなどで家族に簡単に共有できるサービスもあります。
また、サービス機関に先に家族に共有するタイミングを伝えておくことで、亡くなった後にどのタイミングで誰に共有するかなどを設定でき、確実に情報を伝える準備ができるサービスも豊富です。
紙の遺言書やエンディングノートの場合、相続人が見つけられなかったり、失くしてしまう可能性もあるので、しっかり残して、確実に伝えるには、これらのサービスを利用すると良いでしょう。
デジタル遺品は最低限にしておく
使っていないアカウントやサブスクなどがあれば、生きているうちに削除しておくようにしましょう。
また、使っていない口座があったり、複数口座を持っていたりする場合も、口座の数を減らしておくのもおすすめです。
特に、ネット銀行は窓口対応がないので、相続時に親族が困るケースがあります。店舗窓口のある銀行にしておくことで、相続もしやすくなり、残された家族の負担を軽減することも可能です。



1年に1回でも良いので、定期的にデジタル遺品になりうるものは整理しておくのがおすすめです。
信頼できる人への情報引き継ぎ
生前対策では、信頼できる人に情報を引き継いでおくことが大切です。
SNSのアカウントやネット銀行、暗号資産など、どんなアカウントを作成しているか生前に信頼できる人に一覧として情報を引き継いでおきましょう。
相続後に、さまざまなアカウントや存在の知らない口座や資産が出てくることで、相続トラブルに発展する可能性が大きくなります。
残された家族の負担を軽減するためにも、信頼できる人に情報共有をしておくことをおすすめします。
亡くなった後のデジタル遺品整理の流れ
ここでは、亡くなった後のデジタル遺品整理の流れについて、解説していきます。
相続者が自分で遺品整理ができる場合と、業者に依頼をする場合に分けて紹介していくので、デジタル遺品整理を検討している人は、参考にしてみてくださいね。
相続者が自分でデジタル遺品整理を行う場合
相続者が自分でデジタル遺品整理を行う場合、それぞれのデジタル機器のIDとパスワードを知っている必要があります。故人からの遺言や生前整理などで聞いていた方は、端末ごとでロックを解除し、データの確認を進めることが可能です。
その中から、思い出の画像・動画などのデータの保存やバックアップ、存在の知らない資産などがないか細かく確認しておきましょう。
バックアップや確認が終われば、各機器の契約解除を行います。スマホであれば、店舗に出向いて契約解除したり、ネット銀行・暗号資産などはネット上で解約手続きを行いましょう。
相続放棄などをする場合、解約は先にしない方が良いなど決まりもあるので、確認してから解約を進めてくださいね。
デジタル遺品整理を業者に依頼する場合
デジタル機器のパスワードがわからない場合は、業者に依頼してデータを抽出してもらうことができます。デジタル遺品整理がサービスがあり、前段で説明した口座やアカウント、画像・動画データなどの抽出が可能です。
実際の利用者の声では、
- 写真や動画など故人の思い出のデータをバックアップしてもらった
- 相続人の知らなかった資産運用のアカウントが出てきた
などがデータとして情報を得ることができたと言われています。
自分で取り出すことが不可能な方は、一度相談して見積もりを取ってみることをおすすめします。相続関係は期限もあるので、早めに対処しておきましょう。
デジタル遺品整理を業者に依頼する場合
ここでは、デジタル遺品整理を業者に依頼する場合の際のポイントを3つに分けて紹介していきます。パスワードがわからない場合や業者にデータ抽出を依頼してもらおうと考えている人は必見です。
業者の選び方
デジタル遺品整理の業者を選ぶ際は、以下のことを注意してみてくださいね。故人の大切な遺品を取り扱うことになるので、しっかり選んでいきましょう。
- セキュリティ・個人情報保護が厳しく管理されている
- 料金形態が曖昧でない
- 過去実績がある
大切な情報なので、セキュリティ対策が厳しく管理されている業者に依頼しましょう。口座などの資産や写真や動画などのデータを抽出して、納品する流れなのでその間で漏れることのない、安心できる業者を選ぶことが大切です。
また、過去の実績も確認するようにしてください。どんなものをバックアップして、抽出してもらったのか、自分の欲しいデータは依頼することができるのか実績から探すことも大切です。
悪質業者を避けるためのチェックポイント
デジタル遺品整理を業者に依頼する場合は、法外な金額を要求してくる悪徳業者もいるので注意が必要です。
よくあるのが、見積もりの時点では10万円程度で、作業後に想像以上に時間がかかったと言われ、追加料金を請求されるケースです。
また、デジタル遺品整理の相場を知らず、前金として数十万円支払った後にロック解除もできず、何もデータが納品されなかったにも関わらず、調査料金だけ取られてしまうケースもあります。
こういった損をしないためにも、事前に口コミや評判を確認したり、ヒアリング時に見積もりと最終的な支払いに差額はないかなどを聞いたりすることをおすすめします。
大切な故人のデータをできるだけ親族と同じくらい大切に扱ってくれる業者に依頼すると安心できるでしょう。
まとめ
デジタル遺品は、スマホやPC、SNSやクラウドなど、私たちの生活に欠かせない情報の宝庫です。しかし、放置すると家族間のトラブルや情報漏えい、契約・金融トラブルに発展することもあります。
生前の準備としては、パスワードやアカウント情報の整理、エンディングノートへの記載、不要データの削除が大切。死後の対応としては、公式サポートや専門業者の利用で安全にデータを整理するのがおすすめです。
デジタル遺品の管理をきちんと行うことで、家族に安心を残せるだけでなく、思い出や大切な情報を安全に守ることができます。
今日から少しずつでも、自分と家族のためのデジタル整理を始めてみましょう。