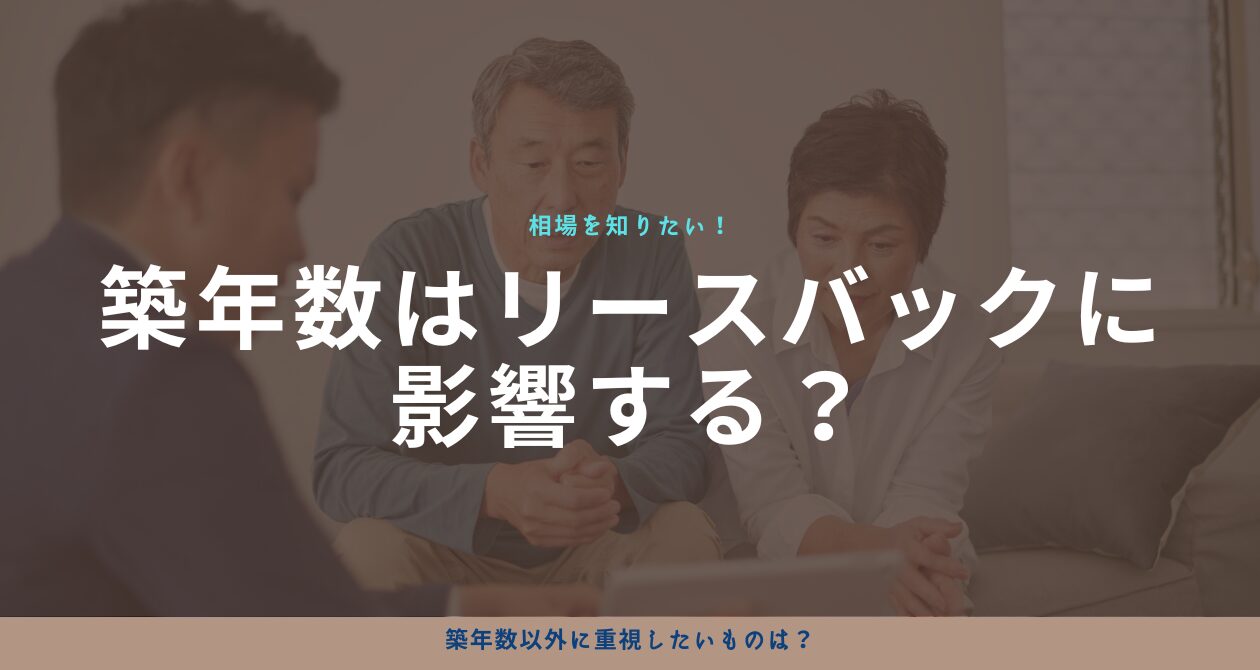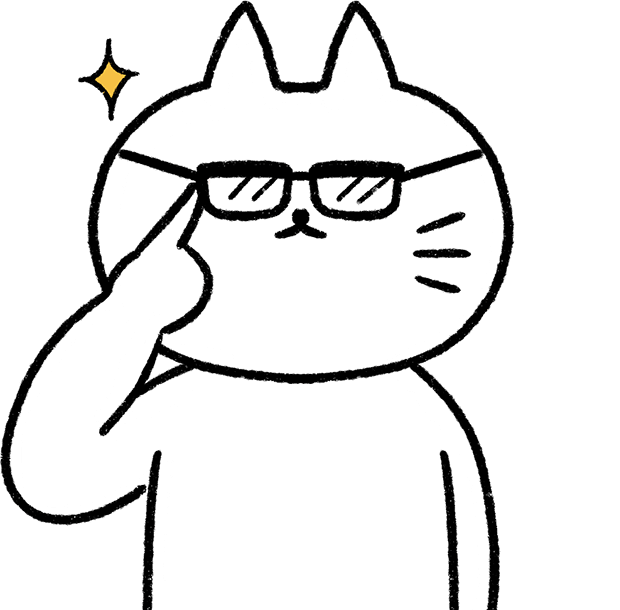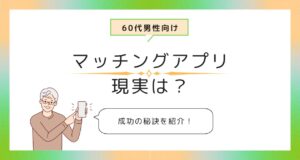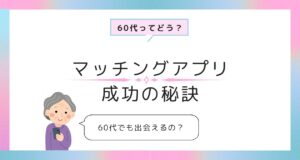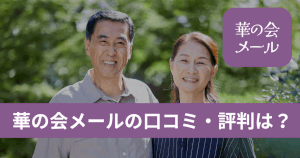うちの家、築35年になるんだけど、こんなに古い家でもリースバックってできるものなのかな?築年数が古いと断られちゃうんじゃないかと心配で…



私も気になっているの!築40年を超えた家だから、リースバック会社に相談するのも躊躇しちゃって。古い家だと査定額もかなり下がるのかしら?
リースバックを検討する際、多くの方が気になるのが「築年数」の影響です。「古い家だから断られるのではないか」「査定額が極端に低くなるのではないか」といった不安を抱える方も多いでしょう。
実際のところ、築年数はリースバックの査定に影響しますが、古いからといって必ずしも利用できないわけではありません。この記事では、築年数とリースバックの関係について詳しく解説します。



こんにちは、不動産担当のこてつです♪
築年数について心配されている方、とても多いんですよね。でも安心してください!確かに築年数は査定に影響しますが、古い家でもリースバックを利用している方はたくさんいらっしゃいます。大切なのは築年数だけじゃないんですよ。
築年数がリースバックに与える影響とは
ここでは、築年数がリースバックに与える影響について解説していきます。築年数以外に何が重視されるかも解説するので、参考にしてくださいね。
築年数と査定額の関係性
一般的に、築年数が古くなるほど査定額は下がる傾向にありますが、これは建物の価値が時間とともに減少するといった不動産の基本的な考え方に基づいています。
ただし、築年数だけで査定額が決まるわけではありません。建物の状態、立地条件、土地の価値、周辺環境など、さまざまな要素が総合的に評価されます。
また、築年数による価値の減少は、建物の構造によっても異なります。木造住宅は比較的早く価値が下がる傾向にありますが、鉄筋コンクリート造などの耐久性の高い構造物であれば、リースバックの際に築年数の影響を受けにくい特徴があります。
築年数が査定に与える影響
- 建物価値の自然な減少
- 構造による影響度の違い
- メンテナンス状況での差
- 立地条件による補正



築年数は確かに影響しますが、それがすべてではありませんよ。きちんとメンテナンスされた築30年の家が、手入れの悪い築10年の家より高く評価されることもあるんです。
リースバック会社が築年数を重視する理由
リースバック会社が築年数を重視する理由は、将来的な転売や賃貸での活用を考えているからです。リースバック会社は物件を購入した後、オーナーが退去された時に第三者に売却したり、賃貸物件として活用したりします。
古い建物ほど修繕費用がかかる可能性が高く、また購入希望者や入居希望者が見つかりにくくなる傾向があります。そのため、築年数は重要な判断要素の一つとなっているのです。
また、築年数が古い物件は、現代の住環境の基準に合わせるためのリフォーム費用も高額になりがちです。これらのコストを考慮して、査定額が決定されます。
会社が築年数を重視する理由
- 将来の転売時の需要予測
- 修繕・リフォーム費用の考慮
- 現代の住環境基準への適合
- 長期保有時のリスク回避
築年数以外に重要視される要素
築年数は重要な要素ですが、それだけで査定額が決まるわけではありません。実際には、築年数以外にも多くの要素が合わさり、総合的に評価されます。
その中でも、立地条件は築年数以上に重要な要素です。
駅からの距離、商業施設への近さ、周辺環境の良さなどが評価されます。特に利便性の高い立地にある物件は、築年数が古くても高い評価を受けることがあります。
築年数以外の重要要素
- 立地条件(駅距離、利便性)
- 土地の形状・面積
- 周辺環境・将来性



そうなんだね!築年数だけじゃなくて、立地も大切なんだね。うちは駅に近いから、もしかしたら築年数が古くても大丈夫かもしれないな。
築年数別リースバック利用の目安
築年数別のリースバック利用の査定額の目安について解説していきます。
あくまでも目安ですが、だいたいどれくらいになるのか把握しておきましょう。
築10年未満:高査定が期待できる優良物件
築10年未満の物件は、リースバック市場では最も評価の高い「優良物件」とされています。建物の劣化が少なく、設備も比較的新しいため、修繕費用も最小限で済みます。
この築年数帯の物件では、市場価格の70-80%程度の査定額が期待できることが多く、大手リースバック会社から地域密着型まで、幅広い会社で積極的に取り扱われています。
家賃設定も市場相場に近い水準で設定されることが多く、売却価格と家賃のバランスも良好です。買戻しを考えている方にとっても、価格の大幅な変動リスクが低い安心できる築年数帯といえます。
築10年未満の特徴
- 査定額:市場価格の70-80%程度
- 取り扱い会社:幅広い会社で対応可能
- 家賃水準:市場相場に近い設定
- 将来性:価格変動リスクが低い
築10~20年:標準的な査定での利用可能
築10-20年の物件は、リースバック市場では「標準的」な築年数帯として扱われます。建物にある程度の経年劣化は見られますが、まだまだ十分に活用可能な状態です。
査定額は市場価格の70-80%程度が一般的で、多くのリースバック会社で取り扱い対象となります。ただし、建物の状態や立地条件によって評価に差が出やすい築年数帯でもあります。
この時期の物件では、これまでのメンテナンス履歴や、主要設備の交換時期などが査定に大きく影響します。適切な管理がされていた物件は高評価を受ける可能性があります。
築10-20年の特徴
- 査定額:市場価格の70-80%程度
- 取り扱い:多くの会社で対応
- 評価ポイント:メンテナンス履歴が重要
- 注意点:状態による評価の差が大きい
築20~30年:条件次第で十分対応可能
築20-30年の物件も、条件次第で十分にリースバック利用が可能です。この築年数帯では、建物よりも土地の価値が重要視される傾向があります。
査定額は市場価格の60-70%程度が目安となりますが、立地条件や土地の広さ、建物の状態によって大きく変動します。特に駅近や商業地域の物件では、築年数の影響を受けにくくなります。
リフォーム履歴がある物件や、構造的に問題のない物件は、この築年数帯でも積極的に取り扱われることが多いです。
築20-30年の特徴
- 査定額:市場価格の60-70%程度
- 評価の中心:土地の価値が重要
- 対応会社:条件次第で多くの会社が対応
- ポイント:立地条件が査定を大きく左右



築20-30年でも対応してもらえるのね。土地の価値が重要ということなら、うちも希望が持てそうだわ。
築30年超の古い家でもリースバック可能
築30年を超える古い家でも、リースバックの利用は可能です。ただし、取り扱い会社は限られ、査定条件も厳しくなる傾向があります。
この築年数帯では、建物の価値はほとんど評価されず、主に土地の価値での査定となります。そのため、立地条件の良い物件や、土地面積の大きい物件が有利になります。
古い家専門のリースバック会社や、柔軟な対応をする地域密着型の会社なら、築40年、50年を超える物件でも相談に乗ってくれる場合があります。
築30年超の特徴
- 査定の基準:主に土地価値での評価
- 対応会社:専門会社や地域密着型
- 査定額:立地次第で大きく変動
- 成功例:古民家や好立地物件



築30年を超えても諦める必要はありませんよ。確かに選択肢は少なくなりますが、古い家を積極的に取り扱ってくれる会社もあるんです。まずは相談してみることが大切ですね。
参考:リースバックの売却価格(調達金額)の基準|不動産リースバック支援センター
リースバックの買取相場、家賃相場、買い戻し相場を徹底解説 | リースバック専門店「イエする」
リースバックで古い家を売る方法!築年数ごとの対策ガイド – 株式会社リアルエステート
築年数による査定額の違いと相場
ここでは、築年数による査定額の違いと相場をより詳しく解説していきます。
立地条件や建物の状態にもよりますが、リースバックの際にある程度の目星にもなるため、確認してみてください。
築年数別の査定額減額率の目安
築年数による査定額の減額率には、一般的な目安があります。ただし、これは建物の状態や立地条件によって大きく変動するため、あくまで参考程度に考えてください。
新築から築5年程度の物件では、市場価格の85-90%程度の査定額が期待できます。築10年では80-85%、築15年では70-75%、築20年では60-70%というように、5年ごとに5-10%程度ずつ減額される傾向があります。
築30年を超えると、建物の価値は大幅に下がり、主に土地価格での評価となります。この場合の査定額は市場価格の50-60%程度になることが多いです。
| 築年数 | 査定額(市場価格比) |
|---|---|
| 築5年以内 | 85-90%前後(好条件で90%台も) |
| 築10年 | 80-85% |
| 築20年 | 70-75% |
| 築20-30年 | 60-70% |
| 築30年超 | 50-60%(土地メイン、もっと下がる場合も) |
木造・鉄骨・RC造による築年数評価の差
建物の構造によって、築年数の影響度合いは大きく異なります。木造住宅は比較的早く価値が下がる傾向にありますが、鉄筋コンクリート造(RC造)は築年数の影響を受けにくい特徴があります。
木造住宅の場合、税法上の法定耐用年数は22年とされており、築20年を過ぎると建物価値の減少が加速します。しかし、実際の住宅寿命は適切なメンテナンスにより大幅に延ばすことができます。
鉄骨造の住宅は法定耐用年数が27年(重量鉄骨)または19年(軽量鉄骨)、RC造は47年とされており、木造に比べて築年数の影響を受けにくくなっています。
構造別の築年数影響度
- 木造:築年数の影響を受けやすい
- 軽量鉄骨:木造より影響が少ない
- 重量鉄骨:築年数の影響が限定的
- RC造:最も築年数の影響を受けにくい
立地条件による築年数の影響度合い
立地条件の良し悪しは、築年数の影響度合いを大きく左右します。駅近や商業地域など利便性の高い立地では、築年数が古くても需要があるため、築年数の影響を受けにくくなります。
逆に、交通の便が悪い立地や、過疎化が進んでいる地域、将来性に人口に伸び悩むとされている地域では、築年数の影響がより大きくなる傾向があります。特に人口減少が進んでいる地域では、新しい物件でも評価が低くなる傾向にあり、注意が必要です。
立地による築年数影響の違い
- 好立地:築年数の影響が軽減される
- 普通立地:標準的な築年数影響
- 不便立地:築年数の影響が拡大
- 将来性:地域の発展性も評価に影響



立地がそんなに重要なんだね。うちは駅から少し遠いけど、商店街に近いから、それも評価してもらえるかもしれない♪
築古物件でも諦めない!査定額アップのコツ
築古物件でも諦めずに、リースバックするにはどうすれば良いのでしょうか?
ここでは、査定額アップのコツを3つのポイントに分けて解説します。
リフォーム歴やメンテナンス状況のアピール
築年数が古い物件でも、リフォーム歴やメンテナンス状況を適切にアピールすることで、査定額アップが期待できます。特に水回り設備の交換や外壁塗装、屋根の修繕などは高く評価される傾向があります。
査定時には、過去に行ったリフォーム内容と時期を整理して提示しましょう。工事の領収書や保証書があれば、より説得力のあるアピールができます。
定期的な点検やメンテナンスの記録も重要です。シロアリ防除の実施、給湯器や空調設備の定期点検、庭木の手入れなど、日常的な管理状況も査定に良い影響を与えます。
アピールポイントの例
- 水回り設備の交換履歴
- 外壁・屋根の塗装・修繕
- シロアリ防除の実施記録
- 設備機器の定期点検・交換



リフォーム歴やメンテナンス記録は、築年数をカバーする強力な武器になりますよ。大切にお手入れされた家は、築年数以上の価値があることを査定員にアピールしてくださいね。
他社で断られた古い家でも対応可能な会社選び
古い家だからと査定を断られても、諦める必要はありません。リースバック会社によって取り扱い基準は大きく異なり、築古物件を積極的に取り扱う会社も存在します。
また、査定額もリースバック会社によって数百万円単位でバラつきがある場合もあります。古い家でも地域性を深く知っている会社であれば、価値があると見做される場合も少なくありません。
地域密着型の会社や、古い物件も取り扱っているリースバック会社では、大手で断られるような物件でも相談に乗ってくれることが多いです。これらの会社は、地域の事情をよく理解し、独自の査定基準を持っています。
また、複数の会社で査定を受けることで、より良い条件を見つけられる可能性があります。最低でも3社程度は相談してみることをおすすめします。
他社で断られた物件も買取可能!
リルエステートのおうちのリースバック
\ 60秒でカンタン無料査定! /
築古物件に強い会社の特徴
- 地域密着型のアプローチ
- 独自の査定基準を持つ
- 古い物件の活用ノウハウが豊富
- 柔軟な対応体制



一社で断られても諦めちゃダメなのね。いくつかの会社に相談してみようっと!
土地の価値や立地条件の活用
記事内でも何度も話している通り、築古物件では、建物よりも土地の価値や立地条件が重要な評価ポイントになります。敷地の形状や面積、接道状況、用途地域などの基本情報に加えて、周辺環境の魅力も積極的にアピールすることで査定額アップを狙えます。
最寄り駅からの距離だけでなく、バス停の近さ、商業施設へのアクセス、学校や病院などの生活インフラの充実度も評価に影響します。また、近隣に公園や緑地があるなどの環境面の良さもアピールポイントになります。
将来的な開発計画や交通インフラの整備予定があれば、それも査定に良い影響を与える可能性があります。自治体の都市計画情報なども調べて、積極的に情報提供しましょう。
土地・立地のアピールポイント
- 敷地の広さや形状の良さ
- 交通アクセスの便利さ
- 生活インフラの充実度
- 将来的な開発計画・インフラ整備
築年数に関するリースバックのよくある質問(FAQ)
築年数を気にし過ぎず、前向きに検討を
リースバックは、築年数に関係なく、住み続けながら資金調達ができる素晴らしい仕組みです。築年数が古いからといって最初から諦めず、まずは専門家に相談してみてください。
きっと皆さんの物件にも、思いもよらない価値が見つかるはずです。大切な我が家を活用して、より安心で豊かな生活を送れるよう、一歩踏み出してみてくださいね♪



こてつくんの話を聞いて、築年数のことばかり気にしていたけれど、他にも大切な要素がたくさんあることがわかったよ。まずは相談してみることから始めてみるね。



私も同じ気持ちよ。築40年超の我が家だけれど、立地は悪くないし、手入れもしてきたつもり!複数の会社に相談して、きっと良い提案をしてもらえると思うから、まずは無料査定を申し込んでみる。



そうですね♪ その前向きな気持ちがとても大切です。築年数は確かに一つの要素ですが、皆さんの大切な家には、築年数では測れない価値がたくさんあるんです。
リースバック会社の中には、古い家の良さを理解し、適切に評価してくれる会社がたくさんあります。大切なのは、そんな会社との出会いです。
一歩踏み出す勇気を持って、まずは気軽に相談してみてください。きっと新しい可能性が見えてくるはずです。
築年数に関する不安解消のステップ
- 現状把握:建物の状態と立地条件を整理
- 情報収集:築古物件に強い会社をリサーチ
- 複数相談:最低3社程度で査定・相談
- 総合判断:築年数以外の価値も含めて検討
築年数のことで一人で悩まずに、まずは専門家の意見を聞いてみることから始めましょう。皆さんの家にも、きっと素晴らしい可能性が眠っているはずです♪
※この記事の情報は2025年9月時点のものです。市場状況や各社の基準は変更される可能性がありますので、実際の検討時には最新情報をご確認ください。